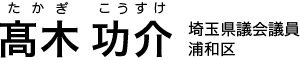2024
これまでの水害対策は、水害を人間の力で抑えることを主眼に置いてきたものであるが、これからは、適切に溢れさせて被害を最小限にすることを目指すものにシフトしているとの指摘に目が覚める思いがした。
人の一生は実感や見聞も含めてせいぜい100年程度が実感する歴史であろう。カスミ堤や輪中は、適切に溢れさせ柔軟に流す流域治水は近世には既に実践されていた技術であるが、温暖化に伴う大規模洪水では、「洪水を抑え込む力が限界に達する」ことに備える意味で再度注目されてきた。また、洪水が発生する場所にはそもそも住まないという事もいつしか忘れ去られている。
令和4年秋に埼玉県議会県土都市整備委員会の視察で「北上川流域治水」事業を視察してきた。溢れさせるという実例では、一関遊水地が挙げられる。遊水地ではあるが、広大な土地であり平素は農地として活用している。この遊水地はカスリン台風の被害を教訓に設置されたものである。岩手県内で死者130名。被害家屋は3096戸を数えた。しかし、この遊水地が完成したのちの大規模水害として、平成14年台風6号、平成19年豪雨でも、遊水地が機能し被害らしい被害はなかった。この北上川は下流に石巻市があり、石巻の水防に有益であることがわかる。もっとも、無計画に溢れさせるのではなく、遊水地の外側には堤防が設けられている。
埼玉県においても、荒川流域が東京の水防として位置づけられていると言われている。実際、荒川の上流の鴻巣市では、川幅が2.5キロにも及びわが国で最も広く整備されている。これは、下流域の荒川の氾濫防止のためである。しかし、住民はこの存在が、首都の水害防止であるとの意味を知る人は殆どいない。行政も全くその理由に触れない。
加えて、河川流域が市街化調整区域に指定され、そもそも人が住まないようにしている。しかし、市街化調整区域は市町村の判断で変更ができ、2000年以降に住宅街になっている場所もあり、流域治水という認知は少ない。荒川流域が市街化調整区域になっている理由を埼玉県として住民に知らしめる必要ももちろんあるが、流域治水は、下流域の水防のために上流域が犠牲になることである。流域治水によって東京が守られていることをもっと活用すべきである。
教授が指摘されたふるさと納税も含めて、そうした地域に金銭的な恩恵が東京都からもたらされるように、私もこの件について精査して議会で提案していきたいと考えている。