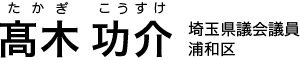2023
わが国の国土面積は約38万平方キロメートル。これは世界61位である。ところが排他的経済水域*1と領海を足した面積は447万平方キロメートルとなり、世界6位の広さになる*2。広大な土地を持つ国家でも、不毛の地ばかりで有効に活用できる土地を有する国は少ない。一方、わが国は、国土の約7割は豊かな森林であり不毛の地はなく肥沃な土地である。そして、海洋には海底資源、海洋資源、水産資源などさまざまな資源がある。わが国は世界有数の豊かな資源大国であり、海洋権益を守る必要性を日本人は再認識すべきであると強く感じる。
さて、海洋権益を守るためには国際間の取り決めが必要である。海洋に関する条約の中で最も重要なものは国連海洋法条約(UNCLOS)である。この条約は1994年11月16日に発効し、2021年3月現在、167か国及び欧州連合(EU)が批准*3 している。国連海洋法条約は本文だけで320条、他に付属書や特別な協定も存在する大きな条約である。こうした膨大な条文になった背景は、海洋の利用について各国の関心が高まり、国益が密接に絡まり、対立が深まったためである。本来なら、各国が二国交渉や条約によって解決すべきものまで、国連海洋法条約に書き込み、この条約を根拠に国益を守ろうとした背景がある。これを見ても、海洋権益が重要なことが判る。
国連海洋法条約では、海を「領海」「接続水域」「国際航行に使用されている海峡」「排他的経済水域」「大陸棚」「公海」「深海底」など様々に分類してそれぞれの海域における権利義務関係を詳細に規定している。また、「海洋環境の保護及び保全」「海洋の科学的調査」「紛争の解決」など海域において行われる活動をその機能について分類し、その基本的なルールを規定している。中でも、紛争解決に関しては、紛争が発生した際、平和的に解決するため、当事国は交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決の手段を選択できるが、紛争の解決に至らなかった場合は、一方の当事国は紛争を強制的に国際裁判所*4に付託することができるとした*5。
また、わが国では、国連海洋法条約に基づき、わが国の海洋権益擁護を目的に、海洋基本法*6を制定している。海洋基本法に拠り、政府は総合海洋政策本部*7の設置及び、海洋基本計画*8の策定を行っている。海洋基本計画は、わが国として実行すべき施策を省庁横断的にまとめ、閣議決定文書として策定したものである。
それでは、尖閣諸島 *9周辺の東シナ海の資源問題を例に挙げて、国連海洋法条約の観点から少し見てみたい。尖閣諸島に限らず、わが国の領土から12海里までは、国連海洋法条約では軍事上の安全保障として規定され、領土と同じくわが国の主権が強く働き、領海に外国船が許可なく入った場合は自国の法律で取り締まれる*10。一方、12海里を超える海域については、経済的な安全保障で規定されている。つまり、国連海洋法条約では尖閣諸島から12海里より先の海域の大陸棚や経済水域の境界画定については、関係国間の合意で決めることになっている。しかし、東シナ海の大陸棚をどのような基準により関係各国で配分するか現在も決着がついていない。国際海洋法裁判所の判決でもあるように、こうした海洋資源の管轄は、境界画定以外にも、資源の共同利用や共同管轄など方法は数多くある。資源をめぐる問題は、各国の国内法や主権的権利に基づく主張を相手国に対して一方的に押し付けて解決できる問題ではないことを関係国は理解しなくてはならない。
海洋権益を守ることは極めて重要であるが、「開かれ安定した海洋」は、世界の平和と繁栄の基盤である。既存の国際法秩序に挑戦する、「力」を背景とした一方的な現状変更を試みる動きに対して、各国が協力して国連海洋法条約をはじめとする国際法を遵守し地域や世界の平和を確保していく毅然とした行動が一層重要となっている。
注釈
*1
国連海洋法条約では、沿岸国は自国の基線から200海里(1海里=1852m)の範囲内に、排他的経済水域を設定できるとしている。沿岸国は、設定水域のその上部水域と海底、及び地下に在る天然資源(生物・非生物を問わない)、水産・鉱物資源並びに、海水・海流・海風によるエネルギー生産に対して、探査・開発・保全及び管理を行う「主権的権利」及び、人工島・設備その他の海洋構築物の設置と利用、海洋の科学的調査または海洋環境保全についての「管轄権」を有する。
*3
米国は国連海洋法条約をめぐる国内対立のため、未だに批准していないが、慣習国際法や国連海洋法条約を尊重した行動を取っている。中国に対する意味からも、批准を求める声は国内外から強い。
*4
付託できる裁判所は国際司法裁判所、仲裁裁判所、特別仲裁裁判、国際海洋法裁判所の4つである。
*5
中国が、いわゆる九段線(海域や島々の領有権を有すると主張してきた破線)に囲まれた南シナ海の地域について、フィリピンが国連海洋法条約の違反や法的な根拠がないとする確認を仲裁裁判所に対して申し立てた仲裁裁判が有名。裁判所は中国に対して「国際法上の法的根拠がなく、国際法に違反する」とする判断を2016年に下した。中国は反発し、判決を無視しているが、米国やフランス・イギリスは、これを踏まえて「航行の自由作戦」として中国に事前通告なしに同海域を航行し、中国の主張を認めない行動に出ている。
*6
平成19年4月20日成立。(1)海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和 (2)海洋の安全の確保 (3)科学的知見の充実 (4)海洋産業の健全な発展 (5)海洋の総合的管理 (6)国際的協調を基本理念としている。
*8
第1期海洋基本計画は平成20年3月18日策定。海洋に関する施策についての基本的な方針、海洋に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を規定。おおむね5年ごとに見直しており、最新の第3期海洋基本計画(平成30年5月15日閣議決定)では、海洋の安全保障と資源活用を重点施策におくなど、積極的姿勢に大きく舵を切った。計画内の施策(約370項目)には予算が付けられ確実に実行される。
*9
尖閣諸島は、戦後、サンフランシスコ講和条約第3条に基づき南西諸島の一部として米国の施政権下に置かれ、1971年6月17日署名の沖縄返還協定によりわが国に施政権が返還される地域を緯度経度で明示した同協定に関連する合意された議事録(公表)の中に含まれている。中国が尖閣諸島を台湾の一部として考えていなかったことは、サンフランシスコ講和条約締結時にも何ら異議を唱えなかったことからも明らかであるが、国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の調査報告の発表後に、台湾当局(1971年6月)も中華人民共和国政府(1971年12月)も、それぞれ初めて領有権を主張するようになった。わが国は尖閣諸島を有効に支配しており、尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在していない。