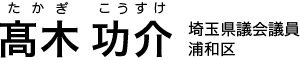2024
問題意識
わが国は2025年に団塊の世代が後期高齢者になり、少子高齢化が一層進む時代を迎える。出生率の向上は、政府が試行錯誤しても思うように伸びていない。男性の育児休暇取得の義務化が法整備され、補助金も世界一の規模を誇る*1が、少子化がどの程度改善できるかは未知数である。だが、高齢化社会は2040年にピークを迎えるまで間違いなく続くことになる*2。そうした社会状況の中で、わが国が経済発展を続け、豊かさを国民が享受出来る社会を築くには、様々な方向からのアプローチが必要である。本稿では、医療福祉政策の観点から、どのようなアプローチができるか考察を試みたい。
検討
健康長寿社会を実現すれば、何よりも、高齢者自身がストレスフリーの生活を送ることができるのが最大の効用である。そのうえ、高齢者の生きがいとしての雇用も期待でき、さらには、社会保障費も抑制できる。そのためには、高齢化に伴う様々な社会的課題解決をし、健康寿命延伸を図ることである。次の4つの視点で検討をしたい。
第一に、地域包括ケアシステムの導入である。これは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムである。これを取り込んだスマートシティ構想も含めて実現していきたい政策である。なお、現在試行されている地域包括ケアシステムの問題点として挙げられるのが、サービスが有効に活用されていない点である*3。また、医療と介護の連携がない点である。そのためにも、医療介護のパラダイムシフトが必要である。そのキーワードは医療介護のデジタル化である。データを活用したAI、センサー、ロボットなどの技術革新を活用が重要である。具体的には、日常生活動作(ADL)モニタリングを用いて健康管理をするシステムとの連動は興味深いと考える。これは、日常動作をモニタリングするものであり、臓器機能の低下によってADL値が連動して低下、それを病院が遠隔でキャッチをし、入院計画を策定するものである。このADL値のモニタリングをしなければ、症状が悪化しバイタルが低下し、最悪の場合、死につながる。これを未然に防ぎ、計画入院することで、軽症で回復することができる。これは現在、実験段階であるが、実用化を注視しているシステムであり、埼玉県として実証実験の支援ができないか、色々と思案中である。
第二に、住民の健康増進とともに医療費削減の両立を図る必要がある。具体的な方策として、データ利活用基盤の整備で健康管理と質の高い医療を提供が挙げられる。オンライン診療によって僻地でも受診が継続できる環境整備、技術革新の実装で介護現場や医師の働き方改革促進、ヘルスケア産業育成への環境整備などが挙げられる。データ活用例として、PHR(Personal Health Record、個人健康記録)とHER(Electronic Health Record、電子健康記録)。先進的なレセプト分析(広島県呉市)が挙げられる。
第三に、70歳までの就業機会確保に向けた法制整備が必要である。そのためには、多様なニーズに対応しうる環境整備、同一労働同一賃金の実施や安全・健康の確保等の土台作り、リカレント教育の促進、労働者のキャリア意識の醸成等である。大企業に対する中途採用・経験者採用比率を情報公開させ促進させる必要もある。
第四に、公的保険制度の改革である。そのためには、後期高齢者の自己負担割合の引き上げ、外来受診時の定額負担、医療提供体制の改革が必要である。また、兼業・副業の課題や労働時間の管理、フリーランスなど雇用に依らない働き方の保護の在り方、不妊治療の保険適用、保険者機能の発揮*4も必要である。
結語
以上のように、わが国が社会保障費を抑えつつ、豊かな長寿社会を迎える術について考察を試みたが、その肝はDX化にあると言えよう。実は、わが国が経済発展を続け、世界有数の経済大国として君臨し続けるにも、DX化が不可避であり、今後、極めて重要な政策になる。そのため、わが国のDX化を推進する施策の方向性について簡単に触れて結語としたい。
わが国がDX化を達成するには、DX化を単に導入するだけではない。仮に外国の技術をそのまま導入するのでは、いつまでたってもユーザーに甘んじ、特に、セキュリティーなど情報が輸入元の外国に流出し、さらには、安全保障も外国に握られてしまう。そのため、DX化には人材育成が何よりも重要になる*5。
文科省では、GIGAスクール構想や「情報」科目などで、デジタル教育を根付かせるために励んでいる。また、コロナ禍でオンライン学習が注目されているが、このオンライン教育を初等中等教育で積極的に導入し、ITに慣れる環境と共に質の高い教育をオンラインや動画で配信することで、教育の均衡が図られ、さらには、向学心を刺激し、幼少期に天才教育が実現できるのではないかと考えている*6。こうした社会を先導する人材育成こそが、超高齢化社会を迎えるわが国の今後の経済発展の要になると言えよう。
注釈
*1
令和3年の改正法案の大きな特徴として、育児のスタートとなる大事な出産直後に男性育休を取りやすくするために、出産日から8週間の間に、4週間の育休を取得できる仕組みを新しく作る。男性も育休を取得しやすくするため、分割して取得できるようになる。この産後直後の4週間の育休は、2回に分けて取得することができるため、「長期間休むことが難しい」という場合でも、繁忙期を避けるなどして取得しやすくなる。また生後8週間であれば、育休取得日数の半分を上限に、仕事をすることも認められる(労使合意が必要)。在宅ワークが普及する流れの中「育休中でもある程度、仕事ができる」ということで、取得しやすくなることを想定している。家計としては収入の上乗せが望める。育休中の収入については、これまでと同様に休業給付金がハローワークから支給されることになる。金額は育児休業開始時の賃金の67%(開始から7カ月以降は50%)だが、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が免除される。実際の支給額は収入の8割程度が育休中も保障されている。支給額には上限があり、最初の6カ月では約30万円。7カ月以降では約22万円。
*2
総務省「国勢調査」、総務省「人口推計」(平成25年10月1日現在)、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果
*3
埼玉医科大学緩和医療科研究チームの報告によると、埼玉医科大学救急センターに救急搬送された高齢者が介護保険を利用している割合が2割以下であった。
*4
重複受診、重複投薬、過剰検査の解消、風邪に抗菌薬を無駄に処方する医師をチェックする必要があり、調剤薬剤師によるレセプトのチェックに期待している。
*5
プログラマー、セキュリティー技術者、制御系の技術者の養成は喫緊の課題であり、筆者は埼玉県議会本会議において、若者制御系技術養成の施設の創設を主張し、実現させた。(「埼玉県議会議事録 令和2年2月定例会 一般質問」(最終アクセス2021年6月30日))
*6
埼玉県立浦和第一女子高校では、新型コロナウイルス感染症防止のための学校休業の際に1800本もの動画を作成し、生徒に開放したところ、学校が再開した時には、実際の授業を先取りして学習し終えた生徒が数多くいたとのことである。(令和2年11月視察時の校長へのインタビュー)筆者は埼玉県議会本会議において、オンライン授業の利活用を積極的に導入するように働きかけている。(「埼玉県議会議事録 令和2年12月定例会 一般質問」(最終アクセス2021年6月30日)