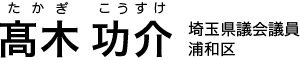2024
自分の葦の空洞から物事を見ると、自分の範囲しか見ることが出来ない。組織がもつ暗黙の「雰囲気」と戦う能動的意識が必要である。
大きな組織は、それぞれの組織内人の分業によって成り立っている。ある事象に関してはリスクが高いと言える場合が多々ある。エンジニアの感覚と一般市民の感覚が違うことがある。一般人に無用な不安を与えないために、0.1パーセントのリスクを安全と言ってしまう。これは間違いではないが、技術者は、「安全は0ではない」ということを肝に銘じないとならない。福島第一原発も然りであり、スリーマイル島原発事故など先進国においても原発事故があったにもかかわらず、対策を怠った。技術者の中には、更なる安全対策の必要性を実感したものもいる。「安全対策が不十分であることの問題意識は存在した。しかし、自分一人が流れに棹をさしてもことは変わらなかったであろう」という意見が多かったという。勇気を振り絞り、自分の意見を言うことは「空気を読まない」行為であるが、それは日本社会の悪い面であり、勇気を技術者は持つべきであろう。
講義では、将来のわが国の技術工学界を担う我々学生に対して、自分がそのような立場に立ったら、勇気を振り絞り自分の意見を言えるか、と問われていた。実際、社会に出ると、家族を養うために会社をクビになること、組織内で生きづらくなることへの恐れから、口をつぐむものも多いであろう。しかし、エリートであるならば、勇気を持たなければならない。その気持ちを新たにさせてくれた。「内心〇〇」では、という逃げは、社会的影響力のあるエリートなら絶対に避けなければならない。エリートの腐敗は亡国へとつながる。わが国が軍部の台頭を許し、国を滅ぼした折の無責任政治家の轍を踏んではならない。
加えて、組織として技術倫理を担保していくには、広い組織でディスカッションして、広く議論すべきである。組織として説明が出来るようにすべきである。上司が技術者に責任転嫁をさせるようなことではなく、価値観のジレンマ内で判断をすることが有る場合、自分の価値観を相対化することが重要であろう。価値中立で考えねばならない局面で、「そのようなことがおきては困る」という先入観や「起きないで欲しい」という期待感も含め、自らの主観的・願望・期待を混ぜてしまってはいけない。客観的事実を直視する冷徹(cool head)さが必要である。一方、世の中には様々な価値観・規範が併存することを認識し、如何なる価値観に基づいて決定し行動するのか、他者に説明できなければならない他者の価値観や痛みを想像できる人間性(warm heart)が必要である。