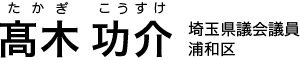2024
耐性菌防止はD\SDGsと深いか関係がある。特にSDGsの17の目標のうち「健康」「安全な水と衛生」が最も関係が深いと考える。
このことは、講義中にも下⽔中の耐性遺伝⼦の存在頻度と社会経済指標との関係において、関連性が指摘されたものである。講義でも薬剤耐性については、中心をなす「健康」「貧国」と「食の安全」「安全な水・衛生」「経済成長」「教育」「研究開発」「国際協力」と関係が示されていた。私はこの中でまず、「健康」は何よりも重要であると考える。2050年の死亡原因のトップが薬剤耐性菌によるものになると予測されている。このことから考えても人類の健康である保健分野との関連は深い。途上国において、現状では、貧困層の医療が課題となっており、この耐性株発生の原因の一つが、適切な医療行為がされずに、自らの判断で安価なペニシリンなどを購入することが問題となっている。つまり、薬品の管理が出来ていない地域をなくすることがこの課題解決に不可欠なのである。また、河川の浄化は感染症予防にもつながるが、耐性菌の防止にも極めて有効である。
「安全な水と衛生」については、耐性ができる経路において、人類の糞尿が適切に処理されないで排水され、その排水が自然循環され抗体を持った細菌が作られてしまうというものである。講義でも、この状況を知り愕然とした。そのため、「安全な水と衛生」が最も関連が深いと言える。細菌は他の微生物から身を守るために何らかの物質を産出する。抗菌薬は人間がそれを模倣して作ったものである。その物質から身を守る機構を持つ耐性菌も自然界に存在する。抗菌薬に耐性を示す細菌が前もって存在するのは当然です。単一の抗菌薬を使いつづければ多数の感受性株が駆逐されて耐性株が生き残り(選別され)、増殖するのも当然である。
SDGsの「安全な水と衛生」は、世界を見れば現状については、人間が出す排水のうち、80%が汚染除去を受けないまま河川や海洋に放出されている。トイレや公衆便所など基本的な衛生施設を利用できない人は40億人と言われている。このような現状下では、薬抗生物質がそのまま自然界に放出され自然界で耐性菌が培養される確率が非常に高いことが分かる。また、講義でも示されたが、わが国の医療のような医師が抗生物質の処方を適切に行うようにしている国ばかりではなく、処方なしで薬局にて手頃に買える国が存在する。しかもこうした衛生環境が整っていない途上国である。こうした国が媒介となって耐性菌が増殖し、コロナウイルスの蔓延のように人類の脅威になることがあるのではないだろうか。
一方で、抗菌薬の発見と開発は1個の抗菌薬開発に10億ドルかかるのと言われ、大手のアストラゼネカ社やノバルティス社すら撤退する状態である。その状況を打破する意味でも、SDGsの「安全な水と衛生」は深い意義があると言えよう。